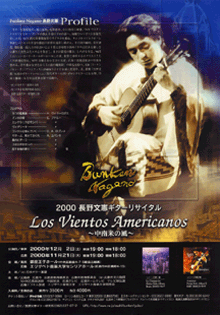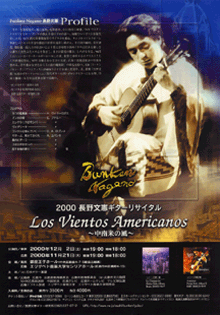| 【作曲者曲目紹介】 |
| YUPANQUI
アタウアルパ・ユパンキ(1908〜1992) |
| 作詞作曲家、ギタリスト、歌手および語り手、エッセイストそしてすべてのフォルクローレ・アーティストの師。ブェノスアイレス州(アルゼンチン)に生まれる。その不断の研究と思索、深く鋭い視察眼、伝統を踏まえた高度な表現力を備える数多くの作品は、ユパンキがアルゼンチンの大地と人間のすべてを実際に識りつくしていたことを物語っている。「歩む大地」と呼ばれアメリカ大陸の生んだもっとも代表的な芸術家である。晩年はパリに定住しヨーロッパを舞台に創作活動を続けた。 |
|
◇ギターよ教えておくれ/A.ユパンキ 長野文憲編 |
|
|
アタウアルパ・ユパンキ作詞作曲のミロンガ。政治的な理由で圧迫された時期の作品。
「誰もが自分は変わらず、変わるのは他人だと信じている。やさしい真実だったものが冷酷な嘘に変わってしまう。…そして私は夜明けをむかえる、一筋の光を待ちながら。夜はどうしてこんなにも長いのか。ギターよ、教えておくれ。」という歌詞がついている。 |
|
◇バルガスのサンバ/アルゼンチン民謡 A.ユパンキ〜長野文憲編 |
|
|
フォルクローレの最古典曲で、アンドレス・チャサレータ採編で名高い。ラ・リオーハ市近郊にあるバルガスの井戸での、リオーハとサンティアーゴの民兵が戦ったとき(1867年)に、サンティアーゴの軍楽隊がこの曲を奏して志気を鼓舞したといわれている。 |
|
◇風のビダーラ/A.ユパンキ 長野文憲編 |
|
|
ユパンキは1956年、自作の小説「セロ・パージョ」を踏まえ、「石の地平線」と名づける1篇の映画を作った。音楽はすべてユパンキのギター・ソロによるもので、これはヴェネツィアの国際映画祭において音楽部門の大賞を受賞した。この曲はその映画のひとこまに用いられたものである。 |
|
◇コオロギのサンバ/A.ユパンキ 長野文憲編 |
|
|
ユパンキが歌うために作ったサンバらしく、出版楽譜は歌とピアノのためになっている。しかし彼自身は「私が歌うのには声がふさわしくないから」と、ギター・ソロでしかとりあげなっかた。長調のノスタルジックな美しいサンバ。 |
|
◇恋する鳩の踊り/A.ユパンキ 長野文憲編 |
|
|
窓辺で恋を語り合う鳩の様子がギターで表現されており、チャカレーラ風のリズムをもち、ギター独奏曲として有名。フォルクローレのギター奏法を昇華した、独自の美しさをもつ。 |
|
|
|
| FALU エドゥアルド・ファルー(1923〜) |
|
ギタリスト、作曲家、歌手。サルタ州ガルボン(アルゼンチン)に生まれ22才の時首都ブェノスアイレスに移る。既にギターの名手であったが、オリジナル「タバカレーラ」をマルタ・デ・ロス・リオスが「カンデラリアのサンバ」をロス・チャルチャレーロスがヒットさせて作曲家として広く認められる。又「ビダリータ」「ビジャンシーコ」「コンドルは飛んで行く」等の名編曲はクラシックギターの技法を越えた不滅の作品である。現代のフォルクローレの音楽的発展に寄与した屈指の功労者といえよう。 |
|
◇ビダリータ/アルゼンチン民謡 E.ファルー編 |
|
|
ビダリータ(小さな人生)とは恋人に対するよびかけだが、アルゼンチン中部からリトラール地方にかけて知られている民謡形式の名前でもある。アルゼンチンで最も有名なビダリータの旋律を、美しいトレモロを生かしギター用に編曲したもので、ファルーの出世作のひとつ。 |
|
◇カンデラリアのサンバ/E.ファルー 長野文憲編 |
|
|
ファルーと詩人ダバロスがサルタ州のあちこちを放浪して歩いていたころ、カンデラリア村の友人の農場で作った曲。青春のロマンティシズムに溢れた名作である。天才ギタリスト・歌手エドゥアルド・ファルーが持つ作曲家としての天禀を決定づけた作品。 |
|
◇インカの母/E.ファルー 長野文憲編 |
|
|
インカの母とは、インカ帝国を構成した土着民の信仰する「パチャママ」と呼ばれる女神のこと。その母なるパチャママをもってしても救えなかった、哀しいインカ滅亡の歴史が歌われている。エドゥアルド・ファルーが、同郷の詩人セサル・パルディゲーロの詞をえて書いた名作で、ウァイノのリズムと、五音音階にもとづくメロディーを持つ。 |
|
◇郷愁のプレリュード/E.ファルー |
|
|
ファルーが書いたギターのためのオリジナル曲。彼の作風は、フォルクローレの形式の上にクラシックの手法を取り入れたものだが、ここでは完全なクラシックの様式を用いて作曲している。しかし、旋律や表現には強くアルゼンチンの感覚と味わいが残っており、魅力的な小品となっている。 |
|
◇コンドルは飛んで行く/D.A.ロブレス E.ファルー編 |
|
|
クラシック畑の作曲家、民俗音楽研究家としてペルー音楽に貢献したダニエル・アロミーアス・ロブレスが作曲したサルスエラのための曲。発表後この旋律は民謡として流布し、南米では早くからスタンダードな名曲となっていたが、1970年サイモンとガーファンクルのヒットにより世界的に流行した。ファルーがこの曲をとりあげ、彼の最高傑作とも言うべき不滅のギター編曲を行なったのは1960年前後のことである。 |
|
|
|
| VILLA-LOBOS エイトル・ヴィラ=ロボス(1887〜1959) |
|
作曲家、指揮者。リオデジャネイロ(ブラジル)生まれ。1905年頃から民謡の採集を始める。1907年国立音楽研究所に入り、ブラジル奥地の風俗・音楽の本格的な調査研究を行なう。ブラジル音楽の特異な性格にふれて1915年以後自らの作品に強い民族的個性をうち出すようになる。1918年ミヨーに会い印象派の手法を知る。1923年よりパリに留学、ロンドン、ヴィーン、ベルリンなども訪れる。1930年以後民謡収集を完成。作風は、ブラジル原住民の音楽に根ざした野性的なもので、かれの創造したショーロスは本質的にブラジル原住民の民俗音楽の特徴を含むものである。 |
|
◇5つの前奏曲/H.ヴィラ=ロボス |
|
|
この曲集は1940年に出版され、ミンジーニャ、すなわちヴィラ=ロボス夫人に捧げられた。もと6曲あったと言われるが、1曲は紛失し、今日に至るまで発見されていない。5曲はそれぞれ味わいを異にした新鮮な感覚美に満ち、近代ギター曲中の名作として愛奏されている。 |