『長野文憲ギターリサイタル』
〜イベロハポネス・ラテンの夜〜
会場/広島市東区民文化センターホール
賛助出演/佐川峯(バンドネオン)、河内敏昭(タンゴギター)
〜イベロハポネス・ラテンの夜によせて〜
高校時代、街の小さな楽器屋で見つけた一冊の楽譜がきっかけでフォルクローレに興味を持ち、それ以来ユパンキやファルーの作品を私のレパートリーとして少しづつ取り入れてまいりました。昭和57年に評論家平岡正明先生に出会い、ユパンキを聴いていただいたのが縁で、私にとって全く未知の分野であったタンゴの大御所、阿保郁夫・河内敏昭両先生との共演が実現しました。その教えていただいたものを自分の肉とするのに数年を費やしましたが、その間に私と中南米音楽とのかかわりが更に深くなったような気がいたします。
今回はずっと平行して勉強してまいりましたクラシックの分野からヴィラ・ロボスをプログラムに入れております。彼の作品はクラシックギターのレパートリーとして一般に定着しておりますが、中南米音楽を通してアプローチしてみて、これまで見えなかった彼の作品の崇高さそして重厚さをあらためて感じております。今回のリサイタルは私が二十数年かかわってきた音楽の集大成
であり、また次への新しいステップになればと考えております。
〜長野文憲さんと私〜
この9月末、久しぶりに長野文憲さんから電話があった。近くまたリサイタルを開くことになったが、その中のヴィラ・ロボスを聞いてくれないか、とのことである。わたしはギター専門ではないが、好きな作曲家であるし、例によって喜んでお受けした。ここ暫く、氏の演奏を真近で聞くことはなかったのだが、最初のプレリュード1番の出だしで少なからず驚いた。音がすべて、16分音符の一つに至るまで、生きているのである。敢えて申すが、弦楽器(ヴァイオリン属も含め)奏者には、ただ弦をならすだけで楽器が共鳴していない人を多く見かける。氏も嘗ては
些かそのきらいがあったのは事実である。それが今回は大きくかわり、楽器のすみずみまで血が通っている感じであった。いろいろ心身のご苦労があったことと思う。現役時代からリュート、またはギターとの室内楽合奏を望んでいた私は、定年後の昭和56年に広島に移り、石井健五氏の紹介で何人かのギタリストの方達と、バロックを主としたアンサンブルを教会などで演奏することが出来た。然し殆どはその時だけで終わり、引き続き交友が続いているのは長野氏だけである。氏が昭和57年に安佐南区・緑井で、フルートの沖中さんとされた初のリサイタルは強く心に残る。そのひたむきな、周囲の目に関係なく、自分で自分を追い込んでいくような純粋さに感動した。
牛田教会で、氏とボッケリーニのギターと弦の五重奏曲“マドリッド帰営”を演奏出来たのも一生の思い出になった。そして練習本番を通じ、この楽器の音域の広さと、如何ともしがたい彼我の音量の差を痛感したものである。
今晩のヴィラ・ロボスは私の好きな作曲家の一人。ブラジル人だがピアノのルビンシュタイン、作曲家のミヨーと知り合い、フランスの勲章レジオン・ドヌールも貰っている。その作風は民族調の中にも毅然とした構成力を持ち、一連の“ブラジル風バッハ”の第5番では、珍しいセロの8重奏を用いている。1966年(昭和41年)、N饗は中南米の演奏旅行を行った。ブラジルの首都リオで私は、何人かの仲間とヴィラ・ロボス記念博物館(と言っても文部省の建物の一画にあった)を訪ね、未亡人と話す機会を得た。婦人が、政府はもっと夫の功績を評価すべきであると、何度も強調しておられたのが、強く印象に残っている。一昨年は我が国でも、氏の生誕百年記念演奏会が行われたが、当広島ではあまり記憶にない。我が国で、氏の作品をあまり取り上げぬのは残念である。単に中南米のフォーク音楽としか映らないのであろうか..... 長野氏は今回日本音楽家ユニオンに参加された。プロの道は依然として険しいが、更に一段と飛躍・成長されることを、仲間の一人として熱望する。
N響団友 吉江澄夫
プログラム
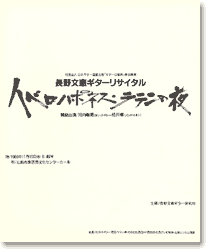
第一番ホ短調 抒情のメロディ
第ニ番ホ長調 カパドシオの歌
第三番イ短調 バッハへの讃歌
第四番ホ短調 インディオへの讃歌
第五番二長調 社交界への讃歌
ギターよ教えておくれ
牛車にゆられて
過ぎし日のミロンガ
木枯らしに泣く小枝
こおろぎのサンバ
コンドルは過ぎ行く
恋する鳩の踊り
さらば友よ
淡き光に
フェリシア-幸福-
ラ・パジャンカ
エル・チョクロ
パリのカナロ
カミニート
アディオス・ノニーノ
7月9日
たそがれのオルガニート
ラ・クンパルシータ